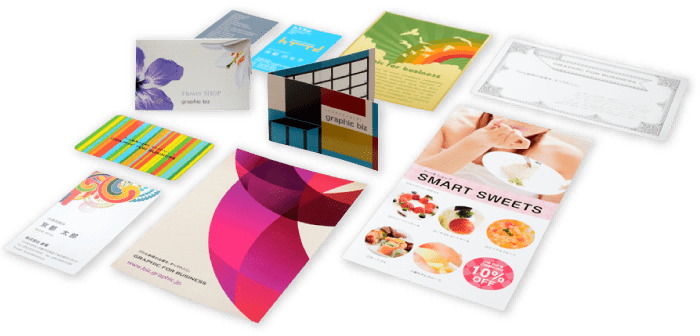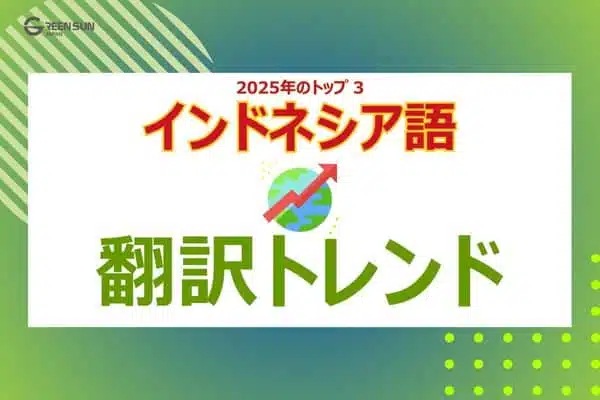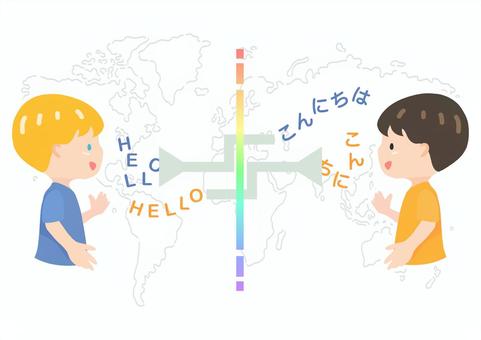DTP作業で制作したデータを、最終工程を受けもつ印刷会社へ渡すことを「入稿」といいます。通常、入稿以降の作業は印刷会社が担当するため、事前の打ち合わせが必要です。ここでは入稿から印刷までの流れをみていきましょう。
印刷のためのハンコをつくる
印刷機で印刷物をつくるためには「版」、つまりインキをつけて用紙に押しつける(圧力をかける)ためのハンコが必要です。通常、版は「製版フィルム」を元にしてつくられ、直接印刷機に取り付けて刷る作業に使用します。このため「刷版」と呼ばれています。オフセット印刷では、「PS版」と呼ばれる非常に薄いアルミの板に製版フィルムの内容を転写し、刷版をつくります。カラー印刷の場合、CMYKという4色のインキで別るため、各色ごとの刷版が必要です。
DTP作業は、製版フィルムをつくるためのデータを作成する作業です。したがって、DTPが導入された印刷工程であっても、製版フィルムを作成してからの作業は、従来の工程と基本的には変わりはません。しかし、DTPでは「イメージセッタ」という機械から製版フィルムを出力する段階で「面付け」が行えるなどの利点があります。また、近年では製版フィルムを出力せずに、DTPデータから直接刷版を出力する「CTP」がかなり普及してきました。
版ができたあと、「校正刷り」という試し刷りを行い、最終の確認作業をします。実際の印刷と同じインキで刷るため、これを「色校正」と呼びます。修正する必要がある場合は、製版フィルムを作成する前の工程まで戻り、DTPデータを修正します。1色刷りで色の確認をする必要がない場合は、製版フィルムを利用して紙を感光させた「青焼き校正」を作成して、校正刷りとして確認作業に使用します。修正の内容によっては、製版フィルム上での修正も可能ですが、最近は修正したDTPデータから製版フィルムや刷版(CTPの場合)を再出力する場合が多いようです。
印刷とその後の工程
最終確認が終了した版は、印刷機に取り付けられ、必要部数のまいよう印刷に移ります。印刷には、カットした用紙に印刷する「枚葉印刷」や、ロール紙を使用して短時間で大量に印刷できる「輪転印刷機」などが使われます。面付けされた状態で印刷されたあと、折り加工、製本加工、断裁などの工程を進んで、わたしたちの手元に届く状態に仕上げられます。
Q&A: 出力ショップって何?
Q: 出力ショップって何ですか?個人でも利用できますか?
A: 主にDTPデータから製版フィルムへの出力サービスを有料で行っているところです。サービスビューローとも呼ばれます。印刷会社に「データ入稿」ではなく、「フィルム入稿」をする場合などに利用します。たいてい個人でも利用できます。規模によっては、画像のスキャニング印刷など、DTPに関連するさまざまサービスを受けることができます。
豆知識
最近では、製版フィルムの修正を行える技術者の減少や、製版フィルムを切り貼りで修正する「ストリップ修正」に使用するストリップフィルムの生産が終了したことなどから、製版フィルム上での修正は激滅しています。
用語解説
- 製版フィルム
刷版の元になるもの。DTPでは、イメージセッタを使うことで、レイアウトデータからカラー分解したフィルムを直接出力カすることが可能になった。
- 刷版
印刷機に取り付ける版。製版フィルムからつくる。オフセット印刷では、薄いアルミの板に感光剤を塗布したPS版が使用れる。
- 面付け
ページものの印刷では、1枚の紙に複数のページを印刷する。面付けとは、製本されたときにページ番号の順番が揃うように並べること。
- DDCP(Direct Digital Color Proofer)
DTPデータから直接刷版を出力するCTPでは、製版フィルムが存在しないため、DDCPで出力したものを色校正とする場合が多い。
- 青焼き校正
1色刷りの校正用に、製版フィルムをジアゾ感光剤を塗布した紙に直接焼きつけたもの。実際に刷られる部分が濃い青色で焼きつく。「青焼き」、「青校」とも呼ばれる。
(続く)
続き読む: